[Necessary evil]
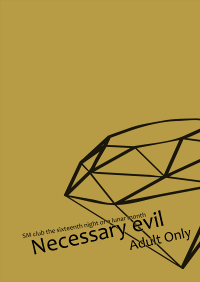
◆J.GARDEN38新刊
R-18
コピー本/28P/200円
会社員とSMクラブ所属のM奴隷という両面を持つ永見は、後輩の男に求愛されていた。優しくしたいという男に絆されかけるが――
R-18
コピー本/28P/200円
会社員とSMクラブ所属のM奴隷という両面を持つ永見は、後輩の男に求愛されていた。優しくしたいという男に絆されかけるが――
電話を取った永見の手首に見えた赤いものが何なのか、そのときは何も知らなかった。
「永見さん。外線一番、ライト社の大滝さんからです」
「はい――お世話になります、永見です」
涼やかな声。それは昼休みが終わったばかりで少し気だるい雰囲気が流れるオフィスに凛と響く。受話器を取る手は白くてほっそりと長く、指先まで神経が通っていると感じる。スーツに包まれていてもどこか浮世離れした美貌。見惚れるとはこのことだと、斜め前の席から今日もこっそりと見つめていた。
だから気づいた。きっと、それを見たのは三芳だけだ。
ぴんと伸ばした腕。その瞬間、普段はスーツの中に着込んだワイシャツで隠れている、華奢すぎる手首が露になる。そこにあるのは白く滑らかな肌ではなかった。何か引き攣れたような赤。一瞬で何も分からなかったけれど、白すぎる肌にそぐわないその色だけが三芳の心の中に残った。
永見は三芳の五つ年上で、同じ部署の先輩だった。彼は都内でも有数の国立大学を卒業、出世街道を走るエリートで、仕事もプライベートも率がないともっぱらの噂だ。残業もほとんどせず、飲み会にも顔を出さないことから『孤高の』とあだ名をつけられることもしばしばだったが。だがその後ろにつけられるワードといえば『クールビューティー』だったり『アイスドール』だったりと、褒め言葉とも言えるものが多い。氷のような涼しい美貌というのはどういうものなのだろうと、噂でしか知らない状態の三芳もはじめは思っていた。その疑問は、永見の顔を見た瞬間に理解した。切れ長の瞳やすらりと伸びた鼻、赤く薄い唇。それを包むなだらかな頬のライン。個々のパーツもすばらしいが、そのひとつひとつが絶妙の位置にある。どこも歪んでいない、まっすぐ綺麗な人。
三芳はこの会社にいる者の大半はそうであるように、永見に一目置き、そして一線を引いた。平凡な自分たちとは全く違う存在であると、自然に理解した。
そんな永見のプライベートに繋がるかもしれない『歪み』を発見してしまったのは、三芳にとっては僥倖なのか不幸なのか。少なくとも三芳は初め、それを見間違いとして脳内処理した。永見の手首に赤い――傷のようなものがあるということは。自傷癖、などというネガティブなワードは瞬時に頭の中から消し去られ、なかったことになった。きっと永見を心酔するこの会社の大半の人間はそうやって納得してしまうだろう。自分の目の方がおかしかったのだと。
「三芳、ちょっと資料室に付き合ってくれないか」
そっけない声音で頼まれて、三芳は一も二もなく請け負った。永見は重い資料を運ぶとき、後輩の男をよく誘う。彼が非力なのではない。身長も平均程度はあるれっきとした成人男性なのだが、重い資料を運ぶことを周りの人間が許さない。口さがない総務部の女性陣はまだ優しい方で、厄介なのは上層部の役員たちだ。永見を幹部候補と崇めたてる、三芳からしたら下僕にしか見えない壮年の男たちは、永見が重い荷物を持っていようものなら同じ課の男たちを容赦なく口撃する。それを永見も分かっているから、重い荷物を運ぶときには誰かに必ず声をかける。それは三芳だけではなく、永見の下にいる数人の男たちに分け隔てなく与えられる責務だ。だが嫌がるものは誰もおらず、まるで花に引き寄せられる蝶のごとく、部下たちは心なしかふらついた足取りで永見の後を追いかけることになる。
「は、はいっ……!」
三芳も例外なく、浮ついた心地で席を立つ。今週で永見に声をかけられるのは二度目だ。資料室へ付き合う頻度が、三芳は他の者に比べて多い気がする。それは五期下ということが理由かもしれない。一期や二期下だと気を使い、恐らく永見が教育係を勤めただろう気安い三期、四期下は、ちょうど今伸び盛りだ。重要な仕事を任されていつも忙しそうにしているから気を咎めるだろう。
だから入社して三年目の、雑用係を外れ、とはいえ慎重を期す仕事を任されるには少し早い三芳と同じ年頃の男は声をかけやすいのかもしれない。更に言えば大型犬によく例えられる三芳の人懐っこさや、どこから見ても恵まれたといえる体格なども、別の対象に入っているのか。
廊下を歩く永見の二歩後ろ。前に進むたびにさらさらと揺れる黒髪を三芳は見下ろす。平均身長ほどの永見に対し、三芳は扉の縁に頭をぶつけそうになるほどの長身だ。加えて大学時代にスポーツをやっていなかったはずはないと言われるがっしりとした体格で、イージーオーダーでないとスーツが合わない。短くするとそこらじゅうに跳ねるので少し長めにしている髪も犬の毛のようにごわごわとしていて、何もかもが永見とは正反対だ。
- ≪ prev