[Subordination2]
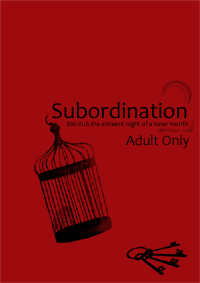
◆J.GARDEN43新刊
R-18
コピー本/24P/200円
夜野田の庇護のもと安寧に浸る生活だが、過去を知る男に会い無くした記憶を思い出しそうになる。夜野田は再び調教を開始する。M男×S調教師続編
R-18
コピー本/24P/200円
夜野田の庇護のもと安寧に浸る生活だが、過去を知る男に会い無くした記憶を思い出しそうになる。夜野田は再び調教を開始する。M男×S調教師続編
アンダーグランドな世界すら桜色に染め上げる四月。散った桜の花びらがここ『十六夜』の地下に存在する入り口まで入ってくるようになるのはいつものことだった。特別な人間しか持つことができない会員カードを所持した者たちの服や髪に花びらが紛れ込むのもこの時期ならでは。
「いらっしゃいませ、佐野様」
「やあ、久しぶりだね、イレブン」
目元と身分を仮面で覆った国会議員が朗らかな笑顔で入店した。彼の服の襟もとにもまた、薄い桃色の花弁がついていたが、夜野田はそれをあえて指摘しなかった。夜中この奥の中に篭りきりになって仕事を行うキャストたちには、こういうサプライズは意外と好評だ。
「お久しぶりです。予約のお時間が迫っておりますので、本日はこのままご案内させていただきます」
「ああ頼むよ。悪いね、最近こちらでゆっくりする暇もない」
赤いベルベットの絨毯が敷かれ、アンティークのテーブルセットにバーカウンターが設置された店内。男は名残惜しそうに顔を見回し、酒や食事を楽しむ男女を羨ましげに見やった。
「いえ、『彼』もお待ちかねですよ」
夜野田は耳打ちする。すると男は仮面の向こうの相好を崩した。男はいつも同じ相手を選ぶ。テレビや新聞で目にする温厚そうな見た目や言動とは裏腹に、ここではサディストが過ぎる男の荒っぽいセッション。それを好む担当ボトムから甘い苦言を漏らされたことがあることはおくびにも出さない。
「はは、そうか。それは嬉しいな」
バーラウンジとなった『表側』と、アーチ状になった扉の奥に息づく『裏側』は、同じ店であるはずなのに全く違う顔を見せる。
「いってらっしゃいませ、良い夜をお過ごしください」
扉を開けて、男を見送りながら夜野田は芝居がかった口調と仕草で頭を下げた。
ご予約のお客様がセッションを終え、店を出るまでが開店時間。今日も最後のキャストが仕事を終え、客を送り出すのを待ってからバーラウンジの扉を施錠した。夜中というよりは明け方と言える時間。たいていこの時間まで残っている幹部は夜野田だけなのだが、すでに帰宅したキングこと十倉とは違い、今日はバーテンダーのもとで酒を楽しんでいたらしいクイーンが、丁寧に頭を下げて客を見送った夜野田のことを見ていたらしい。くるりと振り返った夜野田を、くすくすと上品な笑い声が迎えた。
「相変わらずあなたのその仮面っぷりは、ある意味で惚れ惚れするわね」
「いやだなあ、仮面って。俺は何もつけてないよ」
「ついているじゃない。千とまでは言わなくても、百はありそう。ああこわいっ」
往年の少女漫画を例に出し、その身を抱きしめてくねくねと腰を揺らすクイーンは、仕事や商談中の圧倒的な女王様ぶりとは全く結びつかない。身につけているものは目が覚めるような白地のイブニングドレスに、大ぶりの桜の刺繍が入った豪奢なものだというのに。言動がまるで妙齢女子のようだ。
「ところであなた、ワンちゃんがお待ちかねなんじゃない?」
「そうかもね」
カフスボタンを外しながらそっけなく言えば、クイーンはつまらなそうに唇を尖らせる。
「やあね、つまらないわ。あなた、もうちょっと惚気てくれてもいいのよ?」
「いいの?」
待っていたとばかりに楽しげな笑みを浮かべる夜野田に、クイーンはそうこなくっちゃと長いまつげを瞬かせる。
「聞かせて! ああそういえば、あなたのワンちゃん、結局おうちの会社に就職したんでしょう?」
「そう。面白かったみたいだよ。一人称や口調、まなざしまでまるで違うから、取締役の父親が目を白黒させていたみたい」
夜野田は昨年の夏、この店を冷やかしに来た派手な大学生グループの中から『彼』を見い出し、やや強引な手段で自分のものにした。暗い部屋に閉じ込め、ひととしての皮をすべて剥ぎ取ってしまったら、そこに残ったのは可愛い夜野田の犬という新しい姿。
「変わらず俺のことを待っているけどね、あのときちょっと強引にしすぎたかな? 時間の感覚がいまいちつかめないままだから、朝起こすのが大変だよ」
「あらあ、あなた、一緒に暮らしているの?」
一体いつの間に、と目を白黒させるクイーンに対し、
「違うよ。言っても帰らないんだ」
そう答えると、はあっと大げさな溜息を吐かれた。
- ≪ prev