[Honey moon.]
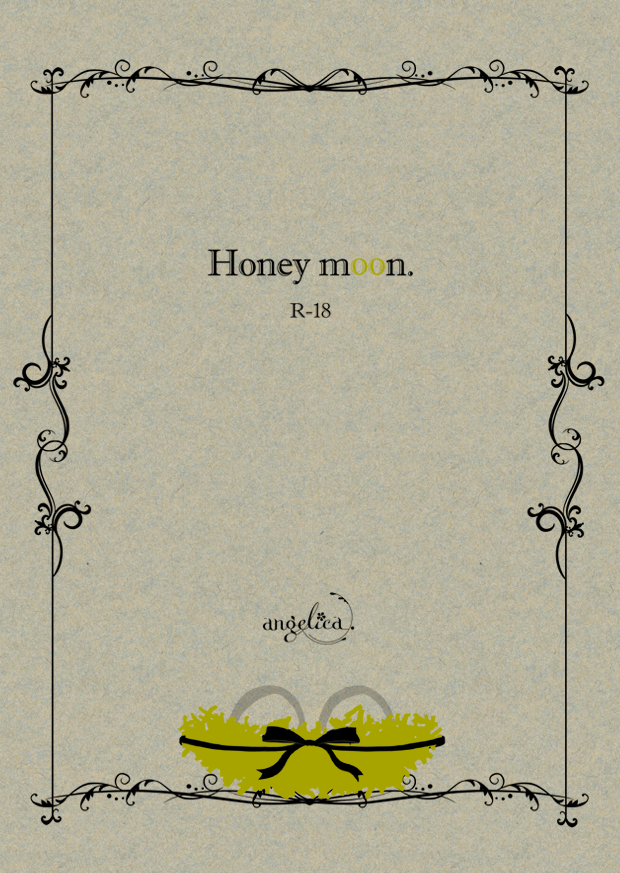
勇ヴィク本
文庫/194P/R-18
五枚の金メダルをとった勇利に、新婚旅行へいこうと提案するヴィクトル。勇利は、そこでサプライズ結婚式をしようともくろむけれど、それがヴィクトルを不安にさせて……。最後はハッピーエンドです。
挿絵をときしらず様に描いていただきました!
文庫/194P/R-18
五枚の金メダルをとった勇利に、新婚旅行へいこうと提案するヴィクトル。勇利は、そこでサプライズ結婚式をしようともくろむけれど、それがヴィクトルを不安にさせて……。最後はハッピーエンドです。
挿絵をときしらず様に描いていただきました!
1
お気に入りのエプロンをつけて朝食づくりに励むヴィクトルの隣で、調理のサポートをすることにも随分慣れていた。この短い時間に一日のスケジュールや今後の楽しい予定について話し合うのが恒例化して随分経つ。
柔らかい朝日が差し込むサンクトペテルブルクのキッチン。勇利は冷蔵庫から出したばかりで瑞々しいサニーレタスを、一口大に千切ってボウルに積み重ねていた。
「だから、俺たちはふたりとも引退したんだし、長めの旅行へ行こうよ。……新婚旅行、ね?」
今日の話題は、ヴィクトルが旅行に行きたいと言い出したことから始まっている。
「旅行ねー……」
ヴィクトルは家にいるのが好きだと思っていたが、よく考えれば買い物となれば目を輝かせるし、子供の頃から世界中を飛び回っていて各地に知り合いもいる。会いたい人もいただろうに、この数年はずっと勇利の隣にいてくれた。これまでは競技者であった勇利に合わせてくれていたのだと遅まきながら気づいて、ふと手を止め顔を上げた。
ヴィクトルは楽しげにベーコンを焼いている、けれど。
勇利は日本で暮らした緩やかな日々の方が非日常だったのだと、いつもうっかり忘れてしまう。もうサンクトペテルブルクに住み始めて、四年も経つというのに。
互いの指に嵌まる指輪はもう随分と傷がついている。同じ年数つけているはずなのに勇利のほうに傷が深いのは、普段の意識の違いか。ヴィクトルが右手の薬指につけているものは、今日も光を反射してきらきらと美しく光っている。
「勇利、卵取って」
「あ、うん」
ベーコンがカリカリに焼けているフライパンを器用に回しているヴィクトルは、この数年で料理もめきめきと上達していた。
ずっと食事の管理を頼んでいた、フードコーディネーターへの依頼内容を変更し、朝食は自分で作ることに決めたのはヴィクトルが引退したばかりのころ。
これからは何でも自分でやってみたいと、楽しそうに浮かべた笑顔がすぐに頭に浮かぶ。
今日はベーコンエッグと、昨日多めに焼いておいたブリヌイをメインに、勇利が千切った野菜、あとはフルーツでもあれば十分。毎日大して代わり映えもしない朝食なのに、いつも作っているときはなんだかわくわくしている。原因が隣に立っている人なのは明白だった。
フィギュアスケート界の絶対王者だったヴィクトルが、手慣れた手つきで料理をしているのは、いつ見ても新鮮だと思う。
勇利は、競技を引退したら世界が変わってしまうような気がしていたけど、日々はそう変わらない。正直こんなものか、という印象を抱いていた。
シーズンになったら未練がふと湧き上がるのかもしれないが、今はまだグランプリファイナルのアサインすら出ていない四月。感傷に浸るにはまだ早すぎる時期だということもある。
だがそれ以上に、ヴィクトルが引退したときに、ヴィクトルが変えて、一緒に暮らしている勇利も同時に変えることになった生活に、いつの間にかすっかり慣れてしまっていた、というのが大きな理由なのだろう。
それにしても。
(新婚旅行……)
頬が熱くなる気がして落ち着かず、勇利はヴィクトルに見えないように口角を緩め、足の裏を逆のふくらはぎにこすりつける。
世界選手権で五枚の金メダルをとったら結婚。
そんな口約束を本気にして、走り抜けた四年間。勇利はリビングルームに飾られている、五枚の金メダルのことを頭に思い浮かべた。
あのバルセロナで銀メダルをとったグランプリファイナル―そしてそのシーズンの最後、世界選手権で一枚目の金メダルを手にした勇利は、そこから四年間、途中でヴィクトルの最後を見送りながらも、頂点を維持し続けたのだった。
(良くとれたよね、何度でも思うけど……)
毎年毎年、激戦と言われる。実力を持ったスケーターが揃っている男子スケート。そんな中で勇利が世界選手権を五年間制覇できたのは奇跡に近い。その他の試合での勝利を捨てる覚悟で、ピークをそこへ合わせ続けていたのだ。
世界選手権で五枚の金メダルをとったら結婚……。
(……ところで、結婚って、旅行へ行くことだったっけ)
ヴィクトルの言葉はなんだか妙だった。
(新婚旅行じゃなくて、結婚式のほうがいいんじゃ。ああ、でも静かに挙げることはできないだろうな……)
ヴィクトルだけでなく、ヴィクトルに追いつき、追い越したこともあった勇利に対しても、世間の目はかなり熱っぽい。特に、今はヴィクトルに並ぶ世界選手権五連覇という偉業を成し遂げたばかりであり、電撃とも言える引退を決めたばかりだからか、取材やテレビ番組の特集、自叙伝の執筆、果てはドキュメント映画撮影へのオファーなど、目の眩むような提案が引きも切らなかった。
フィギュアスケートの世界選手権、五連覇同士が一緒に暮らしているせいか、相乗効果を産んでしまい、あのヴィクトルですら引くほどの取材攻勢が続いている。だから、ロシアにいると煩わしいからと、新婚旅行をだしに逃避行をもくろんでいるのかと思った。
世間がうるさくなりすぎるとヴィクトルは勉強だなんだと理由をつけて、勇利を静かなダーチャや国外へ連れ出していた(結局、勉強なんてせずにダーチャやホテルの中から出ないことも多かったけれど)
だが、鼻歌交じりにベーコンと卵を焼いているヴィクトルの美しい横顔を見ていると、今言っているのはそういう意図があってのことではないと分かる。
日本にいた頃も合わせると五年も隣にいて、鈍いと言われる勇利でも、ヴィクトルの表情は読めるようになっていた。
多分ヴィクトルは、この国では本当の意味で結婚することができないことを、分かっている。だから結婚式をすっ飛ばして、新婚旅行へいこうと言ったのだろう。結婚式は国の承諾が必要だが、新婚旅行に法律はない。
自分たちが新婚旅行だと言えば、そうなるのだから。
「うん……良いかもね」
「何? 勇利、お皿取ってー」
電気コンロのスイッチをオフにしたヴィクトルはフライパンを片手に、完成したベーコンエッグに注視していた。勇利は覗き込んで「美味しそう」と言い、近くに出してあった白い皿を手渡しながら続ける。
「旅行、行こうよ」
感激したヴィクトルがうっかり取り落とさないように、勇利はぎゅっと握りしめた皿を離さないまま言った。
「……ほんと? 勇利は、面倒って言うと思ってた」
「そんなにひどくないよ。だって、新婚旅行なんでしょう」
一生に一度くらいはちゃんとやるよ。そう言った僕に、ヴィクトルは「一生に一度だけじゃなくて他でももうちょっと乗り気になってよ!」と文句をつけたけれど、すぐに嬉しそうに微笑んで、朝食を食べながら計画しようと張り切りはじめる。
そのうきうきした様子が可愛くて、勇利は朝っぱらだというのにどうしようもなくヴィクトルに触れたいと思ってしまう。じっと見ていたら、ヴィクトルは耳の後ろにさらりと前髪を払いながら、恥ずかしげに言った。
「……もう、勇利……すごい目してるよ」
ヴィクトルは目元を染めながら美しく微笑んで振り返り、シンクの縁に腰と手を当てた。柔らかそうな胸を突き出すようなポーズ。あからさまな誘い。勇利はすくい上げるように、背の高いヴィクトルに抱きついた。耳に引っ掛けていただけの前髪はそんな些細な衝撃ですぐに降りてしまう。
「んっ……」
抱きしめると、甘やかな声が頭の上から聞こえてきて心臓がドキドキと高鳴る。
すぐに柔らかな腕に抱き返され、勇利は手を伸ばしてヴィクトルの背を撫で下ろした。腰の辺りで指先が引っかかる。指先をくぐらせると、すぐそれがエプロンの紐だと気づいて、そういえば、このエプロン姿も物凄くそそるんだと思い出す。
こんなに近いと見えやしないけれど。
「ヴィクトル……」
勇利はといえば、起き抜けのスウェット姿のまま。だから薄っぺらい布の分、距離は近く感じられた。でもまだ足りないと思う。ヴィクトルに直接触れたかったし、欲しかった。
「ね、ヴィクトル……味見させて」
胸元にうずめていた顔を起こし、唇を近づけながら囁いた。ヴィクトルの唇は、さっきこっそりとベーコンの切れ端を口にしていたから、うっすらと油が乗っているのだ。てらっと輝くそこに舌を伸ばしながら近づけたら、ヴィクトルは楽しそうに勇利の到着を待っていた。シンクの縁に乗せられたままの手といい、今のヴィクトルはどうやら優位に立っているスタンスを崩す気がないようだった。
「どうしようかな」
その証拠に、そんな言葉で急に寸止めされてしまった。舌を伸ばしたままの無様な姿で動きを止めざるを得なくなった勇利は、不満げに眉根を寄せる。
ヴィクトルはわざと顔を反らせて首をかしげた。
右手を持ち上げ、乾き始めた舌先をするりと撫でてくる。そして、きゅっと摘まれた。
「……っ」
「やっぱりだめ」
朝食が冷めちゃう。そう言うヴィクトルは挑発的な目をしていた。
ここまで接触を許して、今更拒むなんてありえない。勇利はヴィクトルが腕から抜け出そうとする瞬間を狙い、背中からぎゅうっと抱きしめる。
「勇利……」
「ちょっとだけ、良いでしょ」
「だめだよ、今日は勇利、仕事でしょう……」
何のために早起きしたんだ、と文句が飛び出す。そういえばヴィクトルは今日休みなのだった。だから昨日は夜遅くまで恋人同士の時間を楽しんだし、それなのに朝早くから起こさせた上に朝食まで作ってもらった罪悪感が勇利を襲う。
けれどこんなところで止まれるなら、ヴィクトル・ニキフォロフという人と恋人関係にはなっていないだろう。時には、強引さも必要だ。
「いやだ」
強い言葉で縫い付けて、ヴィクトルの胸元を弄る。エプロンの隙間から手を入れて、白いシャツの上から揉み込んた。
「あっ……!」
白い布の下で慎ましく並んでいる乳首を指の股で擦っただけで、甘ったるい声が聞こえてくる。朝のキッチンには似つかわしくないようで、非常に合っていると思った。過去何度ここで繋がったか。不埒な記憶が脳を掠め、勇利は膨れ上がった性器をぐっとヴィクトルの尻のあわいに押し付けた。
「ん……ゆうりぃ……」
昨晩、すこし無理をさせた。だからヴィクトルのそこはまだ柔らかく蕩けているようだった。勇利を感じて震えたそこは、きっと布の下で息をするように窄まりを開け閉めしている。
じわり、と背中から情欲が走って、気持ちが膨れ上がった。
「ヴィクトル、こっち向いて」
シンクに張り付いている腹に隙間を作るように手をぎゅっと入れ込み、くるりと回転させて、正面から抱きしめ直す。そして今度はヴィクトルの尻に手を這わせた。
黒いパンツの上から大きな尻をぎゅっと掴むと、びくっと震えたヴィクトルは、すがりつくように勇利に抱きついてくる。身も心も預けるような腕の重みを感じ、責任を取るようにぐっと足を踏み込む。
「もうだめ、朝だから……」
なのにヴィクトルはまだ拒んでくる。
だが、スウェットの布地をぎゅうぎゅうと掴んで囁かれても、全く説得力がなかった。
誘っているようにしか聞こえない言葉に頬を緩め、もっと求めるようにヴィクトルの首筋へ唇を寄せる。
「ん……ヴィクトル」
わざと声を出して、ちゅっと軽く吸い付く動作を繰り返す。ヴィクトルの肌理が細かくて白い肌は、触れるだけで気持ち良い。ここに赤いしるしをつけたら一層映えることをもう知っている。強く吸い付こうと、音を立てて唇を離したとき。
「勇利、跡はだめ……」
ヴィクトルはまつ毛を震わせながら拒否してくる。
「どうして?」
「明日、撮影入ったから……」
「ええ……」
不満げに鼻を鳴らすが、続けてヴィクトルが口にした撮影予定の雑誌名は、良くオファーを受けているモード系ファッション雑誌だった。勇利は無視しようと動きかけていた身体をぐっと押しとどめる。
あの雑誌はハイブランドの服を身につけることが多い。大抵は高級スーツだが、時折胸元を開けるように指示されることもあると、勇利も何度かヴィクトルと共に撮影に参加したことがあるから知っていた。
それに、クラシカルなセットと共に、孤高の王のように圧倒的な美しさを醸し出す、あそこの雑誌がする仕事は信用している。自らの欲望で、美しいヴィクトルがまたひとつ世に生まれることを邪魔することはできない。勇利は、腕の力を緩めた。
「しょうがないか……」
「……勇利は、いつもそうやって『ヴィクトル・ニキフォロフ』を取るよね」
「跡、付けて欲しいように聞こえるよ」
未練のような言葉を聞いて、意地悪をするように鎖骨に甘く齧りつけば、ヴィクトルは一瞬怯えるように背を震わせる。嫌がるくせに期待していて、こういうとき勇利は物凄く凶暴な気持ちになってしまうのだ。
とはいえ勇利はひとつ息を吐いて、唇を離した。
―でも、最終的には理性が勝つ。大人になったものだと、こういうときに思う。
「勇利は……最近物分りが良い……」
むっと頬を膨らませて言うヴィクトルについ笑ってしまう。
「そうかなあ……」
むしろ今まさに、飼い犬の手を噛んでいた状況だったじゃないか。
ヴィクトルにはもしや、破滅願望でもあるのだろうかと、最後に背伸びをしてちゅっと口づけながら考える。ヴィクトルは、きっとこのまま強引にいったって、口ではだめだと言いながらも満更でもない顔をする。
(でも結局、強くは求めてこないよね)
結局すこし刺激的な戯れとして片付けてしまう。そういうところを不満に思いつつも飲み込んで、勇利はヴィクトルが手早く白い皿に盛り付けた朝食をトレイに乗せた。
中途半端に追い上げられた股間はすこし怪しいが、気にしなければそのうち収まるだろう。
ふとリビングルームを見やると、ラグの上で丸くなっていたマッカチンと目が合う。このやりとりを無垢な瞳で見守っていたらしい愛犬のご飯も忘れないよう、ドッグフードの袋も取り上げて小脇に抱えた。
「ご飯冷えるよヴィクトル」
「分かってる、食べよ。それに勇利、ほんとに遅刻するよ」
時計を見上げて慌てた。せっかくのヴィクトル手製の朝食を、じっくり時間をかけて味わう時間はなさそうだった。
振付師として初めて仕事を行う日、スケート靴の紐を結ぶ手はいつもよりも少しぎこちなかった。緊張している、と自覚して、わざと意識して呼吸する。
ヴィクトル手製の美味しい朝食は、お腹の中でエネルギーに変わってきている。出がけにキスで見送ってくれた恋人は、眠り直す予定なのか愛犬を後ろから抱きかかえて瞼をとろんとさせていた。今頃は明るいベッドの中でむにゃむにゃと唇を動かしているのだろうか。考えるだけで頬がほころび、すぐにそうではないと気を引き締める。
(……よし、行こう)
時間ちょうどにリンクへ向かうと、そこにはすでにアップを初めているクライアントがいた。何年も変わらない金髪に赤いメッシュ、忙しさからか根元は少し黒かったが、どうしても鶏を思い浮かべてしまうその髪型と、あの頃とは随分と変わった身長とのギャップがすこしだけ面白い。
彼、南健次郎は勇利よりも頭一つ分、背が高くなっていた。十代の成長速度はすごい。見かける度に竹のように、にょきにょきと伸びているのだ。勇利にとって、経った年数を実感する象徴のような存在だった。
「はぁ〜! 憧れの勇利くんに振付してもらえるなんて! おいは幸せばい!」
それもロシアの勇利くんのホームで! リンク中に響き渡る声を抑えようにも、彼は感激の舞をすいすいと踊っていて、捕まえることは難しそうだった。
「南くん、ちょっと落ち着いて……」
怒られちゃうよ、と弱気な声で伝える。リンクの端っこで厳しい目を向けているヤコフコーチをちらちらと気にしながら、リンクの真ん中へ。
南の横に立つと、やはり一瞬大きさに驚く。
「勇利くんばほんとぉにすごかぁ! あのヴィクトルを追い抜いて世界選手権五連覇ばい!」
「いや、追い抜いてないから……ヴィクトルも五連覇だし……というか、ここヴィクトルも良く来るから……日本語とは言えその発言危険だから……」
勇利がこのリンクをホームとしていたお陰で、日本語をすこし分かる者もいるのだ。ただでさえ最初は風当たりも強かった場所だ。何人かのスケーターがこちらを気にする視線を感じて、胃がキリキリと傷んでくる。
やっぱり振り付けの場所にこのリンクを選んだのは不正解だったかもしれない。
(でも、公称ではここがホームリンクだし、それにあそこはまだ……)
「勇利くん?」
気づいたら南がこちらへ来て、顔を覗き込んできていた。
「わ、びっくりした」
腰を曲げないとこちらを覗き込めないくらい身長が高いことにまた驚きつつ、勇利は思った以上の近さについのけぞり、後ろにすうっと滑った。
「どうかしたと?」
「いや、何でもないよ。それより、時間がもったいないから振り付け始めようか」
人が少ない奥の方へ移動しながら勇利は南に見えないように、気合を入れようとぐっと拳を握った。数年前にした約束を果たすため、そして、勇利にとってはこれからスケートを仕事にして食べていくために、南への振り付けという仕事はとても重要だった。
ヴィクトルが引退後にスケート関係の仕事をメインにしているように、勇利もスケートと一生付き合っていく気持ちを持っていた。勇利の最後となった昨シーズンに初めて自分で振り付けをしたフリー曲が好評で、最初に発表したアイスショーが終わってから、非公式の振り付けオファーが数件あった。
その中でも熱心だったのが南で、試合会場で会うたびにその話題を出され、「引退したら」の言葉も言い飽きてきた頃に正式なオファーがあった。それは引退会見の翌日で、勇利はそのオファーを、引退後最初に承諾した仕事とすることに決めたのだった。
ちなみに本人から引退を惜しんでいるのだろう、号泣しすぎて何を言っているか全く分からないメッセージが届いていたのだが、振り付けのオファーはきちんとコーチを通して正式にやってきていて、彼の強かさを感じたのももう一ヶ月前だ。
「ここで手を上げて……そう、もうちょっと威厳を持って、力を込めて」
振り付けは曲を流して一度滑ってみたあと、ひとつひとつの振りやステップを確認していくというごく普通のやりかたを選んだ。自分がヴィクトルに教えてもらったことを思い出しながら、南の動きに自分なりの解釈を込めた修正を加えていく。
「うん、そこは大丈夫。次行ける?」
「はいっ!」
素直な返事に唇を緩め、やっぱりリンクの上は静かで良いと思う。
引退してから勇利の身辺は本当に騒がしい。新たな仕事へのオファーが引きも切らないからだ。スケート関連だけでなく、モデルや芸能人のような仕事を日々こなすヴィクトルがそばにいるせいか、勇利も同じ道を歩むと思い込まれているらしかった。
現役選手からは振り付けのオファー、その中でもジュニア世代からはコーチをと求む声。スポンサーや引退済みのスケーターからは来年のアイスショーへの出演依頼がすぐに飛んできた。テレビ局からのゲスト出演依頼、雜誌の取材はもう数え切れない。日本だけではなくロシアからも声がかかったのは嬉しかったけれど―結局、引退から一ヶ月ほどしか経っていない今、どれもこれも保留にしていて申し訳ないと思いつつもまだ頭が回っていないのが現状だった。
(それに、南くんが送ってくれた来季ショート用の曲を聞いたら、色んな振り付け案が浮かんじゃって仕方なかったし……)
結局勇利は、一ヶ月ほどはマスコミから逃げつつゆっくりと過ごしたと言っても過言ではなかった。ヴィクトルが旅行へ行こうと言い出したのも、きっと色々と決め兼ねている今ならば身体も空けやすいと思ったに違いない。
「勇利くん〜! 今んとこもう一回お願いします〜っ!」
「あ、ごめん。もう一回ね」
つい考え事にかまけて流した演技をしてしまった。南の真剣さに呼応できるよう自分も集中しないと、と思い、そのあとは自らもへとへとになるまで振り付けに熱を入れたのだった。
帰宅すると、ソファの上に旅行雑誌が山積みになっていた。
「わぁ……すごい量」
「勇利、晩ご飯食べてきたんだよね?」
「うん。南くんひとりで来てるから。明日も一緒かな」
振り付けには三日取っている。そのあとは、南は日本へ戻ってコーチと共に解釈を深めていく。勇利もアドバイスを請われれば答える予定だった。
「分かった。俺も明日は雑誌の編集者と、会食になりそうだよ」
離れた場所にあるキッチンで酒の用意をしているヴィクトルと大きめの声を上げて会話しながら、勇利は腰を九十度に曲げてソファの上にある旅行雑誌たちをぱらぱらとめくる。
ヴィクトルがこれまでに購入して本棚に置いてあったものから、新たに本屋へ行ったらしい今年の西暦が入ったものまで、三人がけのソファへ座れなくなるくらいに散らばって積まれていた。きっと目が覚めたあとからヴィクトルは家中の旅行雑誌に目を通し、それだけでは物足りないと本屋まで出向いたのだろう。
ヴィクトルの新婚旅行に対する気合が尋常でないことに気づき、勇利は内心怯んでいた。
「勇利? 晩酌は?」
「えーっと……僕は良いよ」
「そう? 俺はちょっとだけ飲むよ」
「毎晩でしょ」
ヴィクトルが飲まない日の方が珍しいというのに、毎度そうやって宣言するのが少し可愛い。その前に忘れていたとただいまのキスをすれば、唇が冷えていたのかヴィクトルのそれが随分と温かく感じられた。ゆっくりと優しく舌を絡めて、挨拶にしては濃いめの口づけを済ませる。
「ん……、ふぁ、……ぁ……おかえり、勇利」
唇が離れると、ヴィクトルは嬉しそうに微笑んだ。
「うん。ただいま、ヴィクトル」
「あ、何か音楽かける?」
「いや、テレビつけていい?」
ヴィクトルのコレクションとも言える量がある、スケートで使えそうなクラシックから、最近の曲まで取り揃えているCD棚を少しずつ崩していく作業も楽しいのだが、明日の天気予報と今日のニュースを見ておきたかった。
ロシア語を日常的に聞いていないと忘れてしまわないか不安で、勇利はできるだけテレビをつけるようにしている。ヴィクトルとは英語で会話しているし、スポンサーも気を使ってくるから、意外とロシア語を聞く機会は少ないのだ。
「良いよ」
ヴィクトルはテレビのリモコンを操作しながら、ソファの下に敷いてある毛足の長いラグの上に寝そべった。床に置かれたトレイの上にはグラスに注がれた酒と、小さな小皿に盛られたロシアのジャムであるヴァレーニエ、横にはナッツも添えられている。
天気予報は明日も曇り空を示していた。サンクトペテルブルクは晴れの日の方が少ない。
それを確認してからスプリングコートを脱いでクロゼットへかけにいったのだが、山積みの旅行雑誌のことを思うと一瞬風呂と言って逃げ出そうかと魔が差してしまう。
「勇利もこっちおいで。今日はシャワー良いんでしょ?」
しかしリンクでシャワーを浴びて来たのはバレてしまっているようで、ヴィクトルにそう誘われてしまったら戻るほかなかった。
「うん……」
ため息を噛み殺してリビングの扉をくぐると、ソファの上に置かれていた雜誌達はすべてヴィクトルの前に積まれている。プレッシャーを感じて、ごくんと唾を飲み込んだ。
ヴィクトルの右隣で寝そべるマッカチンとは逆側へ、観念して腹ばいになる。するとヴィクトルは喜々として雜誌を勇利の前へ広げていく。
「ねぇ勇利、どこへ行きたい?」
ハワイにグァム、バリにモルティヴ。ヴィラにコテージに、プールと庭付きの別荘。どれもこれもオーシャンビュー、デッキから海へ出られるものも多い。すごいのだと貸し切りの無人島まで―。勇利は圧倒的な情報量に怯む。
「すごい量だね……」
「そう? でも、これくらいあったほうが色々選べるよ」
選ばれているのは概ね、温暖な場所にある島だった。
ヴィクトルの中で旅行とはふたりきりでゆっくりと過ごす、である。ロシアが寒い国だからなのか、ロシア人自体、旅行と言えば暖かい場所という習性があるようだ。
ヴィクトルも例に漏れず、これまで旅行へ行きたいと言うと、ほとんど暖かい国の名前を出している。そこに異論はないのだけれど。
「新婚旅行はふたりきりだから、マッカチンはお留守番でごめんね〜」
そんな声を耳にしながら、勇利はややうんざりした気分でどれもこれも同じに見える青い空と白い砂浜の写真を眺める。
選択というものが勇利は得意ではない。特に、どれもこれも同じに見えるものとあらばなおさらだった。ヴィクトルの「どっちの服が俺に似合う?」という問いかけと同じだ。勇利にはどちらにも同じに見えるし、どちらもすごく良く似合うから決められない。明日の服でさえ選択を怠るとぷんぷん怒るヴィクトルだから、ここで選択をミスするとかなりあとを引くだろう。
テレビでは、若手のアナウンサーが今日のニュースを伝えている。為替や株の話は勇利には縁遠い。つい聞き流してしまい、ハッとする。これでは勉強にならない。勇利は選択と勉強を両方することは諦め、雑誌を見ることに集中した。
(どうしようかな……)
ヴィクトルは新婚旅行を楽しみにしているのが明らかだ。鼻歌交じりにナッツを口にし、酒を飲みながら、抱きまくら状態の愛犬に謝っている姿を見ればすぐに分かる。機嫌が良すぎるヴィクトルは期待をしているから、それを裏切るとまずい。
勇利はにわかにプレッシャーを感じながら、しかし暖かい国で開放的な気分になるのはやぶさかではないとも思う。
(というか、ヴィクトルの水着とか、薄着とか、そういうのは……まあ、いやじゃないし)
むしろ良い、なんて思っていたら、なんとなく催してしまった。うつ伏せのままだと苦しくなってきて身じろぐ。
ヴィクトルは明日仕事だと聞いているけれど、少しくらいなら構わないだろうか。
「……、ヴィクトル」
「ん、決まった? 勇利……っん」
こちらを向いたヴィクトルは前髪が邪魔をして視界が悪い。それにつけ込んで唇を塞いだ。驚いたヴィクトルが目を見開かせているのを盗み見るのは思いの外良いのだ。
勇利は眠そうにしているマッカチンからヴィクトルを奪い、背中に手を回して引き寄せた。温かい身体を抱きしめると、朝、中途半端に催したままなあなあになっていたことを思い出してしまう。今度こそ止まれない。
「ゆうり、っ……んぁ、は……っ」
「ヴィクトル、……」
ゆるゆると背中から腰を撫でつつ、イージーパンツの緩めのゴムをかいくぐって直接尻に手を這わせた。面積が少ない下着を身に着けているヴィクトルの生尻に触れることはあまりにも容易すぎて、つい心配になる。
競技を引退してもスケートから離れることがない生活をしているから、ヴィクトルのそこは現役時代とほぼ変わりない。少し、柔らかくなった気もするけれど―きっとそれは自分のせいだという自覚があった。
「ん、っ……ゆうり、っ、そこ、そんなっ……あぁぁっ……」
張りのある肌を手のひら全体で揉み込む。冷えた皮膚が勇利の手の熱で温まっていくのを感じながら、指先に引っかかる下着を気まぐれに持ち上げては離す。パツン、という恥ずかしい音が響いた。刺激にヴィクトルがもぞもぞと腰を振っていて、それが視界の端で揺れているのがたまらない。
「ヴィクトル、可愛い……」
我慢ができないとねだるような、求愛のダンスさながらの動きにそそられ、勇利は甘ったるいと自覚している声を遠慮なく出して、ヴィクトルを奪いにかかる。
「……、あっ……」
うつ伏せから身体をぐるりと滑らせて仰向けになり、ヴィクトルを下から抱きしめて引き寄せる。勇利を押し倒す形になったヴィクトルだが、その肘はもう崩れてこちらの身体に乗り上げてしまっている。ずっしりとしたヴィクトルの重みが勇利は好きだった。ヴィクトルが全身を預けてくれている。筋力もありプライドもある男であるヴィクトルが全身で甘えてくれるのが、勇利は本当に嬉しいのだった。
「……、ヴィーチャ……良い?」
照れくさくてめったに呼ばない愛称を口にして懇願したら、ヴィクトルは観念したようだった。けれど、小さく唇を寄せてちゅっと音を立ててから、
「ちょっとだけだからね、明日は撮影だし……」
と牽制するのは忘れなかった。
「分かってる。ちょっとだけ……」
「そう言って終わった試しないけどね……」
半ば諦めたような声が聞こえてきたけれど聞かなかったことにして、勇利はヴィクトルの口の中に舌を差し入れ、ちゅう、とわざと音を立てて聴覚を煽った。
「ん、んっ……ふぅ、っ、ぁ……」
くちゅ、ぴちゃ、と水音を立ててする派手なキスは、互いの性感を高めるにはぴったりだった。いつの間にか上下でぴったりと重なり合った性器を、腰を揺すって刺激する。自らのものも、相手のものも気持ちよくて、すぐに硬度を持ってしまう。ヴィクトルのものはいつも勇利より少しやわらかい。だがその分大きくてふわふわしていて、触り心地が良くて好きだった。勇利はイージーパンツの隙間からあっという間に手を差し込んで、ヴィクトルのものへ直接触れる。
「あっ……、ゆうり、ずるい……っ」
勇利はジーンスを履いていて、ベルトを外せないと文句を言うヴィクトルが可愛かった。わざと腰を浮かせ、ぐいぐいとヴィクトルに押し付けて邪魔をしながら、大きくて柔らかい性器を指先で愛撫する。
「あっ! あ、ぁ、ああっ……!」
耳元で無防備に漏れ出る甘い声がたまらない。勇利と身体を重ねるようになって随分経ち、ヴィクトルはすっかり感じやすくなっている。触れるだけで甘ったるい声を、それも勇利の耳元でわざと立ててくるのは、これは悔しさからくる意趣返しなのだ。けれど、それで勇利はすっかり身体が熱くなっていくからちょうど良かった。
「ん、ヴィクトル、僕のも触ってよ……」
「だったら、協力、っ、ん…ぁ…」
「うん……」
キスの合間に悪態をつくヴィクトルがこれ以上気を損ねる前に、勇利は腰をラグの上に落として左手でベルトを外してしまう。あとはヴィクトルが両手を使ってボタンを外し、ジッパーを下ろした。もうジーンズの硬い生地を押し上げるほどに熱くなっていた性器は、灰色のボクサーパンツに生々しい形を浮かび上がらせている。
「ん、勇利のおっきくなってる……」
「当たり前でしょ……」
朝、寸止めされた恨みを勇利は忘れていなかった。
触って、と囁く。
「だめ、待って、マッカチンが起きちゃうから……」
同じラグの上で眠る愛犬を気にしてちらちらと視線を横向かせていたことには気づいていた。たしかに、気持ちよさそうに寝ているのに、ここで最後まですれば起きてじゃれついて来るだろう。楽しく遊んでいると思われるのは良いが、罪悪感もある。
「……じゃあ、ベッドいこ」
「うん、勇利……」
連れて行って、と言われるまでもなく腕を引いて立ち上がらせる。腰に腕を回して引き寄せたら、ヴィクトルは嬉しそうに抱きついてきた。ぎゅう、と抱きつかれるとうっすらお酒のにおいがした。
「お酒、全部飲まなくて良いの?」
トレイの上のグラスは、ほんの少しだけ中身を残している。
「大丈夫、勇利が俺を酔わせてくれるだろ?」
そんなふうに急にかっこよくならないで欲しい。不意打ちで口説かれて頬を赤くしてしまった勇利は、悔しかったのでその言葉に対してのリアクションは取らなかった。
「……ほら、行くよ」
一歩先に進んで、引き寄せるように手をつなぐと喜ぶ。
ヴィクトルは、こういうシンプルな触れ合いが本当に好きだ。
「ふふ、勇利は照れ屋さんだなあ」
世界を魅了する美しい男は、いつだって一筋縄ではいかない。うっかりすると主導権を握られて好きにされてしまいそうになる。組み敷く側としてのプライドが勇利にないわけではない。だが、ヴィクトルに主導権を握られて好きにされるのも楽しいから、結局、勇利のプライドなんてないようなものだ。
それこそ、恋人には骨抜きに惚れている。
「ヴィクトル、早く行こ」
そんなことを考えていたら、ちっとも我慢ができなくなっていた。今日は全部好きにさせて欲しい。ヴィクトルを頭のてっぺんから足の指先まで全部可愛がって、自分のものにしたい。そんな欲望が渦巻いた、焦っていることが分かる掠れ声。
ヴィクトルはいつも、それをひどく喜ぶのだった。
薄暗い寝室でまずしたことは、ヴィクトルの服をすっかり脱がしてしまうことだった。
風呂上がりなこともあり、柔らかい綿素材のVネックシャツに、部屋着代わりのイージーパンツという恰好なこともあって、脱がせるのはあっという間だ。身体に張り付くような黒いブーメランパンツも膝から抜いて、裸にしてしまってから押し倒す。
「ん……勇利は脱がないの……?」
ベッドランプ薄暗い光源だけでも、美しい肢体なのがひと目で分かる。
競技を引退してからも、ちっともプロポーションが変わらない。すこしも老けないその人は、不満そうに問いかけてくる。勇利はシンプルな長袖シャツとジーンズを脱ぐ余裕もなくヴィクトルに乗り上げた。息がすでに荒くて、余裕がないのがひと目で分かる。
「良いから……」
勇利の方は引退して一月、それまで世界選手権に向けて絞っていたせいもあって、ややリバウンドしていた。とはいえ、ヴィクトルが機嫌を損ねるレベルではない。
だから見せられないということはないのだが、今は自身の身体がどうこうというよりも、ヴィクトルに触れたくて仕方がなくて、自分の服まで手が回らないというのが本音だった。
自分よりも大きな男の身体を押し倒す高揚感。ヴィクトルはおとなしくシーツに沈んで、勇利に身を委ねてくれる。
「ん、勇利……やっぱり素肌で抱き合いたいよ……ん、っ」
恋人のささやかな願いを封じるようにキスをして、ぬる、と舌を絡める。ヴィクトルの口の中はほんのりと酒と、甘い果実の味がした。酒と甘味にくらりと脳が酩酊しそうだ。もちろんヴィクトルの口の中に残っているのは僅かだ。
だからこれは、ヴィクトルに触れているからなのだった。
「ヴィクトル……、お願い、触ってよ……」
下着に収まりきらず、先端をはみ出させているもの。取り上げたヴィクトルの手をそこへ触れさせる。ヴィクトルはキスを受け止めながら指先をくの字に曲げて、そこを愛撫した。
「あ……、っ、ヴィクトル……」
「ゆうり、すごく熱いよ……」
ぬる、と先端から溢れる液体をヴィクトルは指ですくって先端に押し付け、柔らかいそこをぐりぐりと弄ってくる。粘膜に直接される刺激にはどうしても弱く、腰ががくっと落ちそうになる。
「ヴィクトル、ヴィクトル……」
勇利はヴィクトルの顔を抱きしめて、キスに没頭する。舌を絡めて吸い上げると、ヴィクトルは喉の奥から掠れた甘え声を漏らした。もぞもぞと足が動く。ヴィクトルも欲情を持て余している。そう思うと全部、可愛がってあげたくなる。
酸欠になりそうな深いキスをやめ、勇利はヴィクトルの手を取り上げて指先に舌を這わせた。ぬるっとした先走りがこびりついた美しい指を、舌で舐めてていねいに拭う。
「あ、勇利……指、」
自分のものがついていることには気づいていたが、弄ってくれたヴィクトルを褒めるように、そこをきれいに舐めて清めた。そして、そのまま指の股に舌を這わせる。
「あ……っ、そこ、だめ……!」
ヴィクトルはことさら右の薬指が弱く、指輪が毎日擦れている指の股はより敏感なようだった。指輪ごと口に含んで根元に歯を立てたら、ぴくりと震えた指先に喉の奥を撫でられてぞわっと刺激が走る。口をすぼめてじゅっと吸い上げたら、他の指に顎を捉えられた。
「ヴィクトル、離して」
「勇利が離したら離す……っ!」
仕方ないと口から指を出そうとすると、ヴィクトルの手も力を抜いた。勇利はそのまま掴んだ手を引き寄せ、唇を指輪に触れさせる。ちゅ、と音を立てて何度も口付けると、ヴィクトルはあっさりと身を委ねてしまう。そんなところが可愛いと思いながらちらりと舌を出して指の股を今度は舌先でちろちろと舐めたら、ぞわっとした快楽が駆け上がったのか、ぴくっと性器が揺れた気がした。
「ゆ、勇利……もう、終わり……」
「まだまだ、これからだよ」
今日はヴィクトルを全部愛するって決めたから。勝手な宣言に驚いたヴィクトルが目を見開いている間に、勇利は手の甲に唇を寄せ、そのまま手首に滑らせた。ぐっと手をそらした瞬間に静脈が浮いたその凹凸を舌先でなぞったら、ヴィクトルは呻くような声を漏らす。勇利は手首を掴んだまま、唇をどんどん滑らせていく。前腕の柔らかい筋肉を唇と頬でなぞり、肘から二の腕は舌を滑らせる。
そのまま脇の下をぺろりと舐めたら、咎めるような声が溢れた。
「だ、だめ、勇利っ!」
それを無視して、良い筋肉が乗って柔らかい肩から、鎖骨まで舌で舐めあげていく。ヴィクトルの肌は滑らかで、甘い気がする。首筋を舐めると汗をかいているのかすこししょっぱかったけれど、勇利には甘みも感じられた。
「う、うぅ……」
信じられないと唇を少し開けているのが可愛らしく、勇利はその口の端にも唇を寄せて、ちゅう、と音を立ててキスをした。
「ヴィクトル可愛い……」
「勇利はすぐ、そう言う……」
ふたりで歳を重ねるごとに、だんだんと口癖になっている気はしていたけれど、恋人が可愛く見えなくてどうすると開き直ってもいた。それに、ヴィクトルはそう言われることが満更でもないらしく、文句をつけるときいつも視線が合わない。
「そういうところだよ」
身体がまた温度を上げる。愛しさを込めて、ヴィクトルの頬に口付けた。そこから今度は耳元へ、耳朶をなぞりながら長い前髪を手で持ち上げ、髪の色のお陰で透けて見える生え際と頭皮も、遠慮なく舌全体を使って舐めた。
「あっ……う、っ……なに、ほんとに何なの、勇利……」
突然、濃いというよりは変態じみた触れ合いを強要されて、ヴィクトルは戸惑っている。勇利の方は朝から焦らされたり、新婚旅行を要求されたりしてじわじわと盛り上がっていった部分があったのだが、ヴィクトルにとっては唐突だったようだ。
「ヴィクトルのせいでしょ」
プラチナブロンドの柔らかな髪にも口付けて、勇利は手のひら全体で頬から首筋をするすると撫でた。それでも、分からないと首をかしげるのが可愛い。
「ね、新婚旅行の行き先……僕が全部決めていい?」
目を見開くほど意外な提案だったらしい。確かに、ヴィクトルから見れば明らかに面倒くさそうにしていたから。だが、勇利の方には結果的に四年も待たせたという負い目が少しあって、ヴィクトルが言い出したことだとしても、それは男の責任のような気持ちをずっと抱いていたのだ。
「どうしたの、勇利……」
本当は色んなことを勇利から決めたかったのに、引退して一月、心が落ち着く前に、ヴィクトルから新婚旅行を提案されてしまった。このまま言われるがままに甘えることは勇利のプライドが許さない。
「何でも。良いでしょ?」
ヴィクトルは、ただ僕についてきてくれればいいから。
そう耳元に囁いたら、ヴィクトルは口を手で覆って、こくこくと何度も頷いた。
ヴィクトルをいつもより濃く愛したいという衝動は抱えつつも、そろそろ直接的な刺激が欲しかった。勇利は、下半身はまた今度、と勝手に決め込んで愛撫を中断する。
「はー……はっ、ヴィクトル……」
硬めのベッドマットの上で膝立ちになって、汗で身体に張り付いていたシャツをぐいっと持ち上げて脱ぎ捨てる。
「……ね、ヴィクトル、もう入れたいかも」
「っ、さっきから、もう、っ……してって、っ……!」
柔らかなキスと舌で舐めるばかりの愛撫で延々と焦らされてしまったヴィクトルは、真っ赤にした頬と浮かべた涙目で睨みつけてきた。
それに、ぞくっとするほどそそられてしまう。
勇利はぐずぐずに濡れたヴィクトルの性器をゆるゆると上下に撫でながら、枕元に手を伸ばしてローションを取り上げた。中身を濡れているところに垂らし、冷たい粘液が絡みついて身体を震わせるヴィクトルを見下ろして、ごくんと唾を飲み込んでから、指先を尻側へ移動させた。
「あ……もうとろとろ……」
尻のあわいにローションで濡らした指先を差し込めば、甘ったるい触れ合いに高まったヴィクトルの身体はぐずぐずに蕩けていた。窄まりくぱ、と伸縮している。勇利の指をずっと待っていたようだ。ローションを更に掬い取ってそこに指を差し込むと、ヴィクトルの身体の力が抜けきっていることもあって、あっさりと第二関節ほどまで入り込む。
「あ、う……」
何度しても、ヴィクトルは最初、異物感に顔をしかめる。背をもぞもぞとシーツになすりつけて、腰を揺らす様は淫靡に見えるけれど、苦しそうな表情を見てしまうと心配のほうが勝ってしまう。
「ちょっと我慢して……」
ヴィクトルにばかり我慢を強いているな、と思いながらも勇利は指をぬるる、と奥へ差し込む。ゆるゆると手を引けば、ローションに濡れた指がぐち、と粘った音を立てて抜き取られた。ローションをまたすくい取り、乾いたそこを濡らしていく。
「あ、あぁ、は、ぁ……ん……っ」
手の甲を唇に押し当てて声を漏らすヴィクトルを見上げる。揺れる前髪が少し濡れていて艶めかしい。顎の形すら美しい恋人をこうしていっぱいいっぱいにさせられるのは自分だけなのだと思うと、ひどい優越感に満たされた。
(ヴィクトルは、そもそもどうして僕に身体を明け渡してくれたんだろ……)
未だに答えを知らない問いかけは、ヴィクトルと勇利が深く知り合うきっかけとなった、勇利の記憶からは消えてしまっている、あのソチでのバンケットルームまで……遡らなければならないのだろう。未だに詳細は教えてもらえないままだった。
ただ、あのとき勇利はヴィクトルを抱いたらしい。
そして、その後日本へやってきたヴィクトルと想いを伝えあった夏、初めて抱いたと思っていた手慣れた身体は、実際は勇利が押し開いたものだったらしいと聞いていた。
(本当に、あの日に戻れるなら戻って全部録画したい……)
一生忘れないように。
ただ、それはもう変態の領域に達する所業ではあるのだが、ヴィクトルと積み重ねた日数の間に、そういったことはすでにやっているのだった。
(まあでも、そういう映像は僕のスマホに入ってるし……)
そんなことをつい考えていたら、ヴィクトルがこちらを見上げて、ぱちぱちと瞼を上下させている。熱に浮かされた大きな身体を持て余して、もぞもぞしているヴィクトルはたまらなく可愛い。
「ゆぅり……、まだ……?」
「あ、ごめん、もうちょっと慣らすよ……」
「ん……うん、……」
無心で指を動かすということはほぼ不可能で、ヴィクトルの様子を見ながら指を二本、三本と増やしていく間に勇利の頭の中に駆け巡ったのは四年前の記憶だった。
ヴィクトルが急に実家へ押しかけてきたのだとずっと思っていたら、実際は記憶にない自分がコーチになって欲しいと依頼していたと知ったとき、勇利は穴があったらそこに入って二度と出てきたくないと思う程に恥ずかしかった。
「そろそろ……良いかな」
黒歴史を封印するように口に出して、勇利はくぷんと音を立てて指を引き抜いた。三本の指を美味しそうに食んで甘い水音を立てているヴィクトルの窄まりを見ていたら、うずうずしてしょうがない。早くこの温かくも先端は柔らかく、根本はきつく締め付けてくる極上の場所に入って、頭がおかしくなりそうなほど気持ちよくなりたかった。
「勇利、顔見せて……」
膝立ちになってジーンズと下着をまとめて膝まで下ろしていると、ヴィクトルの可愛らしい願いが聞こえてきた。勇利は取るものも取り敢えずという余裕のなさで足に絡まったものを蹴り脱ぎ、海にダイブするような激しさで無防備に寝転がっているヴィクトルの身体に乗り上げる。
「ゆぅり……」
いつもよりもかなり長めの愛撫を施したせいか、ヴィクトルはすでに焦点を失ったような蕩けた瞳で、唇も緩んで開いていた。とろ、と溢れる唾液を舌ですくい取る。そのままキスをすると、ヴィクトルは震える腕を勇利の首の後ろへ回した。
「んぁ、は、ぁ……ゆぅり……」
とろとろに溶かしたヴィクトルの身体を抱きしめるのはたまらなく良かった。勇利は沈み込むような快楽に頭をぼやかせ、本能のままヴィクトルの足を持ち上げる。肩に引っ掛けられるほど柔らかいヴィクトルの股関節は引退してもちっとも変わらない。筋肉を包み込んで張りのあった皮膚が全体的に柔らかくなったような気もするけれど、それこそ陶器の白のようにとろりとした色のものが柔らかいとただただ気持ちよく、一生でも触っていたいと思う。
「ヴィクトル、いれるよ……?」
聞こえているのか分からないと思いながらもそう囁けば、小さく頷く気配がして勇利はほっと息を吐く。やっぱり最初に蕩かせすぎると、箍が外れすぎてしまわないか心配になってしまう。翌日に持ち越しすぎるようなセックスはすべきではない。特に今日は。ヴィクトルは明日撮影なのだ。
(でも、一回なら大丈夫……だよね……)
くたりとして重たい足。勇利が触れていない右足はシーツの上にのたうったままなので、ぐっと押し広げた。窄まりが顕になる。ベッドランプだけの明かりでもくぱくぱと伸縮しているのがひと目で分かった。勇利を待ち望んで赤く色づいたそこ。上向いている性器とぶら下がっている果実も、張り詰めて色を変えていた。淫猥な光景に情欲を煽られる。
「は、ぁ……ヴィクトル、ヴィクトル、ヴィーチャ……」
ぐ、と腰を押し込むようにして性器の先端を潜り込ませた。興奮で固くなりすぎているそこは根元を押さえる必要すらなさそうだったが、それでも角度を調整するために指先を添える。触れると実感できる、自分でも笑ってしまうほど硬度を増しているそれ。張り出したカリの部分は先走りでぬるぬるになっていた。
窄まりにそこが触れると、ぐちゅ、といやらしい音がした。
「ぁ、ぅり……ゆ、うり……っんんぁ……!」
仰け反って喉を晒すヴィクトルを見下ろしながら、ふうふうと熱い息を吐く。汗で額にべったりと張り付いている前髪が邪魔で左の手の甲で拭ったら、汗で滑って眼鏡が落ちた。シーツの上に転がったそれを拾うのも億劫で、勇利はそのまま濡れた前髪をかきあげ、ヴィクトルに覆いかぶさるようにしてゆっくりと中に入っていく。
「あ、ぁ、あ……、あ、あっ……」
のたうつように腰をびくつかせるヴィクトルを見下ろしながら、ゆっくりと前へ体重をかけていった。肩に持ち上げたヴィクトルの脚はどこまでも柔らかく持ち上がる。時折びくっと震えてぴんと伸びるのがたまらなくいじらしい。
勇利は足首を捕まえて、土踏まずに唇を寄せた。
「ん……」
ちゅ、と口づけを落とすと、スケーターの敏感な足はそれだけで指先をびくつかせる。
「あ、ゆぅり、そこ、はっ、だめ……っ!」
「気持ち良い?」
「んっ、ん、っ……だめ……」
気持ちいいことは一目瞭然なのに、だめだと首を振るばかりのヴィクトルは、勇利のものを半分ほど受け入れたところだった。
この様子ならばもうちょっと進んでも大丈夫かな。そう脳内でつぶやいて、勇利はぐっと腰を進めた。
「ああっ! っ、ぅり、急に……っ」
足へのキスと腰の動きを交互にして翻弄したら、ヴィクトルは文句をつける余裕もなくなって、途切れそうに儚い息を零す。
「ぁ、っ……ぅ、ぁ、は……ぁう……」
「ヴィーチャ、奥まで入ったよ……」
ぐっぷりと入り込んだ勇利の性器は根元を数センチ残すのみで、黒い下生えがヴィクトルのなめらかな肌に触れていた。そこを見下ろして指で結合部分をなぞると、くぱ、と伸縮してローションがじゅっと溢れる。たまらなくいやらしい様子に頭がくらっとした。
ヴィクトルのために動きを止めて息を整える。急に伸ばされた粘膜や皮膚が慣れるまでじっとしている時間は、ヴィクトルにとってはじくじくした痛みと戦う時間でもあるのだろう。額や頬にぽろぽろ溢れる汗を指で拭ってやりたい衝動に駆られる、だがそれをすると負担をかけてしまいそうで、勇利はただひたすら耐えていた。
(でも、この時間……結構好きかも)
言葉もなく、ただ荒い息だけが交わる部屋の中。ヴィクトルをただただ見つめられる時間というのは意外とないものだ。普段生活している時は会話を欠かさないし、何かに集中している時にじっと見ていたら、気が散ると怒られてしまうから。
だからヴィクトルがスケートを滑っているときと、今こうして待っているとき。それくらいしかない気がする。
「……ゆぅり」
きら、と指輪が光る、頼りない手が伸びてきた。勇利はそれを左手で受け止めた。それは待てが解除された合図でもある。そっと腰を引いて、ヴィクトルの反応を見る。繋がっていない方の手がシーツをぎゅっと掴んでいた。苦しいのかもしれない。足を抱え直し、勇利は様子を見るように腰を再び近づける。
「ぁ……あ、ああ……っく、ぅ……」
「苦しい?」
問いかけると、首を横に振るヴィクトルはかなりいじらしい。苦しいと眉間にしわが寄っているのに。そんな苦悩の表情すら美しくてぼうっと見てしまって、ヴィクトルにばれて睨まれてしまう。
「ヴィーチャは、睨んでても綺麗だよね」
「なに言って、ぁ、っ……!」
ずるる、と腰を引いて黙らせて、勇利はゆっくりと律動を刻み込む。強く締め付けてくる粘膜。溶けてしまいそうになるほどの気持ちよく、正直理性なんてすぐになくなってしまいそうだった。勇利は気を紛らわせるために右肩に抱え上げたヴィクトルの膝小僧に唇を落とした。くすぐったくなるだろう、触れるか触れないかくらいの位置で唇を滑らせたら、ぶるっと身体を震わせる気配がした。
「やぁ、だ……ゆぅり、あんまり……いじめないで……」
とろとろとした声と美しい顔が涙で潤んでいるのにそそられ、勇利はこの瞬間、理性を手放した。ぐうっと腰を曲げて、抱えていた足も下ろして、つないだ手をぎゅっと握りしめて、がつん、と腰を押し付ける。
「ああっ!」
下生えでヴィクトルの会陰をくすぐるように上下左右に揺さぶって、一気に半分ほどまで引いて突き入れた。
「あ、……っ! ゆうり、ゆうり……っ!」
唇をゆるゆると開いて甘ったるい声を零すヴィクトルを見下ろして、こんなにも幸せな時間はないと思う。好きでたまらない、とびきり美しい人が、自分のものを受け入れて気持ちよくなり、こんなにも声を上げているのだ。勇利は汗が滴る額や頬をうっとうしく感じながらも、指を絡めるようにつなぎ直した左手も、ヴィクトルの腰を支える右手も離す気はなかった。
「ヴィーチャ、ヴィーチャ、っ、ヴィクトル……」
唇からこぼれ出る言葉はほとんど無意識だった。甘やかすというよりは急き立てるように呼び、律動はどんどん激しくなる。突き入れるほどに柔らかく、きつく包み込まれ、ぎゅうぎゅうと甘やかしてくれるヴィクトルのそこ。結合部からはぐぷん、ぐちゅ、と淫猥な水音と、勇利が腰を突き入れるたびに肌がぶつかるはしたない音が響いて、耳からもどんどん煽られる。
「あっ、あぁぁ、ぁ……は、ぁぁう……」
ヴィクトルはただ勇利が与える快楽に感じ入っていた。時折うしろを伸縮させているのは、きっと無意識だろう。自分のことでいっぱいいっぱいという感じで、それが可愛かった。
身も心も任されている気がして。
勇利は腰を掴んでいた右手を離し、ふたりの間で蜜を撒き散らして揺れているヴィクトルの性器へと移動させた。触れるだけで敏感なそこはくぷっと先走りを零す。白くてふわふわとした、もともと柔らかめのそこを握り込むと、ヴィクトルはぎゅっと瞼を閉じて宝石のような涙をまつ毛に散らした。首まで真っ赤にして、ぷるぷると首を振る。
「あっ! あ、っ、す……ぐ、いっちゃ、っ……!」
「いいよ、いって、僕ももう……」
ぱんぱんに膨らんだ性器がぎゅうぎゅうと締め付けられている上に、ずっとごしゅごしゅとヴィクトルのおしりの中でこすっているのだ。すぐに終わってしまいそうな予感しかしなくて、だからヴィクトルと一緒にいきたかった。
「ヴィーチャ、いって、ね、っ、も、ぼくも……っ!」
「あ、あ、ああ、っ〜〜……あっ、は、ァっ……!」
ヴィクトルは腹をびくびくっと震わせて、ぐうっと身を屈めながら白濁を零す。
そしてぎゅうう、と粘膜で強く抱きしめられた勇利も、
「ヴィーチャ、っ……!」
そう愛おしい名を呼びながら達したのだった。
- ≪ prev